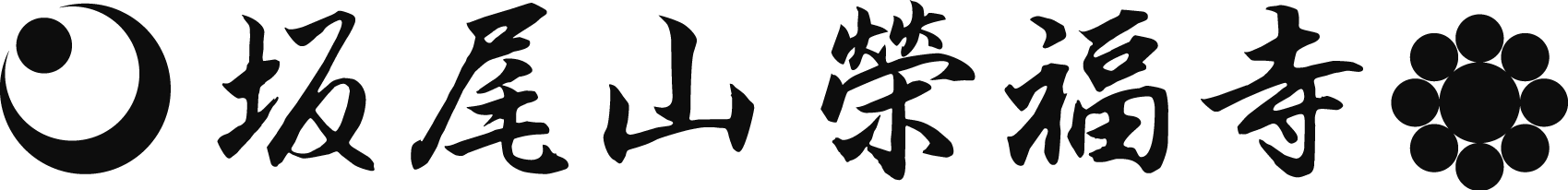当山の宝物は非公開です。
また、「金銅透彫六角釣燈籠」、「紙本著色千葉妙見大縁起絵巻」は、文化財の適切な管理のため千葉市郷土博物館に寄託されております。
お問い合わせは、同博物館へ。
●金銅透彫六角釣燈籠
(千葉県指定文化財・非公開 千葉市立郷土博物館保管)
高さ24.3cm、基盤の最大幅25cmの秀麗な透彫り細工による燈籠で、笠・火袋(火明かりの入る部分)・基盤とも鍍金の銅薄板で作られ鋲留めや差し込みで組み立てられている。笠は一枚の銅板を2段で開き笠になるように作られ、頂上には六葉座に4cm四角の銅板を敷き上に請花を配した宝珠を載せ、吊るすための環台としている。6角柱形に作られる火袋は、各面とも斜め格子地に千葉氏の紋所である九曜星文が透かし彫りされている。1面は蝶番による扉仕掛けとなっており開閉ができる。
基盤の裏面に「奉寄進下総国臼井庄本城妙見堂金灯炉者也 原式部太夫平胤栄敬白 天正二年可甲戌三月二十五日」の銘文が刻まれ、天正2年(1574)に原式部太夫平胤栄によって寄進されたことがわかる。寄進者の原胤栄は、臼井城(現在の佐倉市臼井)の城主で千葉氏の執権として活躍した。原氏はもともと千葉氏の一族で、千葉氏宗家を支えた宿老の一門、胤栄の父で胤貞の代の16世紀後半に勢力を拡大し臼井城の城主となっている。

●紙本著色千葉妙見大縁起絵巻
(千葉県指定文化財・非公開 千葉市立郷土博物館保管)
榮福寺は千葉氏ゆかりの寺院である。中世に房総各地に威勢を誇っていた千葉氏は、妙見菩薩を篤く信仰していた。県内には、その崇敬ぶりをうかがわせる妙見菩薩像がいくつか残されているが、絵巻ではこれが唯一の資料である。
この絵巻は、千葉氏一族が守護神とした妙見菩薩との出会いから、幾多の戦いに妙見の霊験で勝利したこと、そして千葉氏の居城内への遷座といった、妙見に対する信仰の由来を、余白を多く用いて人物や建物を淡泊に表現する画法の絵と詞書で記述した、全4巻の総長約32mにおよぶ大作である。
絵巻の奥書から、享禄元年(1528)に本庄伊豆守胤村が詞書を作らせ、その後天文19年(1550)に詞書と絵を合せて上・下二巻の絵巻として作り直し、延宝6年(1678)板倉筑後守重直が補修をおこなっていることや、詞書はそれまでのものを用いて、絵は狩野探幽の門弟片山三清守長に描かせたものであることなどがわかる。

●木造妙見菩薩立像(千葉市指定文化財・非公開)
檜材を用いた寄木造で、胎内の墨書により天正4年(1576年)の作と知られている。
左右に振り分けた髪は両耳半ばまで垂れ、左手は刀印をつくり、右手に剣を握る。腰をわずかに左にひねり、沓をはいて正面向きの亀に乗って立っている。
千葉氏が信仰したという妙見菩薩の一つの姿を伝える像として貴重である。
●妙見地蔵堂
文久元年(1861)に乗寛師によって再建された。大規模な改造もなく現在に至っている。
建築様式としては、幕末期を代表する力強い彫刻を持ち、建築年代がはっきりしている例として当地域の近世社寺建築の指標となり得る。